研究プロジェクト
磁力計について
磁場観測器の現状、取り組み
磁場は宇宙空間の自然を考える上でとても基本的な物理量です。なぜなら宇宙空間は地球磁場をはじめとする様々な磁場に満たされており、それ自身が変動、ま たは同様に宇宙を満たすプラズマと相互作用をしています。実際にこれまで打ち上げられたin situ(その場)観測の科学衛星には必ずといっていいほど磁力計が搭載され、宇宙の磁場を観測してきました。
という話しをすると、磁力計はもうすでに開発されており、出来上がった物を搭載すればよいと思われるかもしれませんが、実際にはさまざまな宇宙磁場や宇宙 環境に合わせて最適な磁力計をミッションごとに開発してやる必要があります。例えば今進行中のミッションとして水星探査ミッションがありますが、水星の磁 場は現在のところ350[nT]程度の磁場(地球磁場は日本付近で30000[nT]程度、:T[テスラ]は磁場の大きさを測る尺度)を保有していると考 えられています。ですので、磁場が小さい分、高分解能な磁力計(ものさしの目盛りが細かい磁力計)を開発する必要があります。また、水星のある宇宙環境は 太陽からの放射線が強力でまた、温度変化もすごく大きい(衛星の部位によって変わるので一概には言えませんが磁力計はマイナス数十度〜プラス百数十度)の で、それに耐える磁力計を開発する必要があります。
これからの磁場観測器開発
これからのミッションでは今まで以上に観測器に対する低電力化、省スペース化が要求されます。また昔からあったアナログ部品が手に入りにくくなったりする などという困難が生じてきています。そこで、宇宙研では従来の磁力計(アナログ磁力計と呼ぶ)に対してデジタル方式を用いたデジタル磁力計の開発に取り組 んでいます。デジタル磁力計はそれらの困難を乗り越えると同時に、過酷な宇宙環境による経年変化、温度依存を受けなくなるという利点もあります。また、従 来の磁力計よりもより高周波の磁場を観測することもできるようになると予想されます。
高性能なデジタル素子の発達に伴ってデジタル方式の磁力計はこれからどんどん普及していくものと考えます。
磁場観測機の観測原理
実際にどのように磁場を観測しているかについて簡単に概要を説明します。磁力計はセンサーと、センサーの後段にある回路部で構成されています。センサー部 には強磁性体のコアにコイル(ドライブコイルとピックアップコイルと呼ばれる2つのコイル)を巻いた物を使用しています。このコアは磁場が存在する空間に おいて、ドライブコイルに交流電圧(コイルに電圧をかけるので交流磁場をかけることに相当します)をかけると、その周波数の2倍の周波数成分の電圧(2倍 の高調波と呼びます)をピックアップコイルに出すという特徴があります。さらに、その時出てくる2倍の高調波の振幅は、センサーを置いた位置での磁場の大 きさに比例するという特徴があります。したがって、センサーに交流電圧をかけて、出てきた2倍の高調波の成分を調べてやれば磁場を測定することができま す。
以上のような原理で磁場を測定するわけですが、実際に宇宙で磁場を測定するときには、衛星本体から伸展物(日本で用いられているアストロマストという伸展 物は回転しながら衛星本体から数メートルも伸びていきます。回転式ではなく、折畳み式の伸展物もあります)を出して、その先端にセンサーを固定しておきま す。なぜそういうことをするかというと、"衛星自身が磁場を出すから"です。宇宙で磁場を測定しようとしても衛星自身が磁場を出していては、結局衛星の磁 場を測定してしまうことになってしまいますね。ですから、なるべく衛星から遠いところにセンサーを設置することにしています。そうすることで、宇宙空間の 磁場を観測しています。
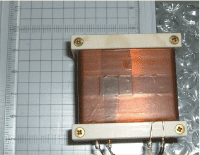
磁力計センサー部
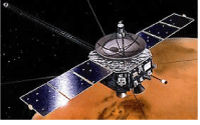
左上部に伸展しています(のぞみ衛星)
ここからはちょっと詳しい説明(進学希望者向)
磁力計のコアには磁性体が使われていると述べましたが、より詳しい説明をします。一般に磁性体では磁場に対して磁束密度は比例関係にありますが、磁場を大きくしていくと比例関係は無くなり、図1のようなB-H曲線と言われる特性を示します。
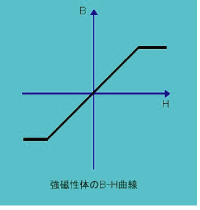
図1:強磁性体のB-H曲線
B-H曲線からわかることは、磁性体にかけていく磁場Hを大きくしていくと、ある決まった値までは磁性体中の磁束密度Bが増大していきますが、ある値を超えて磁場Hをかけても磁性体中の磁束密度Bはそれ以上増大しない値を持つということです。
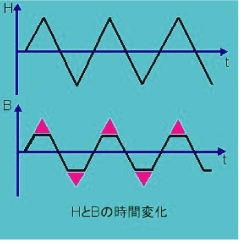
図2:磁性体中の磁場と磁束密度
図2に示したのは磁性体での磁場と磁束密度を時系列で書いたものです。上側が周期的に磁場を変化させた(三角波になるように磁性体中の磁場を変化させた)ものをあらわしており、下側はその時の磁性体中の磁束密度の変化をあらわしています。
磁場がある一定値を越えると、磁場が変化しても磁束密度が変わらないという様子は下側の絵で色付の部分が欠けていることからわかります(磁場と磁束密度が常に比例していたらこのように欠けたりしない)。
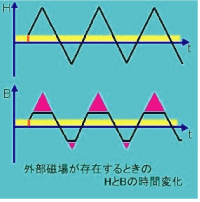
図3:外部磁場がある場合の磁性体中での磁場と磁束密度の変化
では次に、もしこのような磁性体を外部磁場がある(磁場がある)空間においた場合に同じように磁性体に周期的な磁場をかけるとどのようなグラフになるでしょうか。
図3に外部磁場がある場合に磁場と磁束密度がどのように変化するかを示しました。
図3の黄色部分が外部磁場の存在によるオフセット(あらかじめある値を持っている)をあらわしています。よって全体としては、その時の外部磁場(黄色部分 に相当)に対応した大きさの分だけ、グラフが磁場、磁束密度の正方向にずれたような形になります。図3上側の磁場の変化は、正方向にずれても図2のものと 形はかわりません。が、下側の磁束密度の方は「ある一定値を超えると磁束密度はそれ以上増えない」という約束があるため、欠けてしまった部分(色付三角で 示した部分)が変形しています。違いがよくわかるように2者を並べた図が図4です。
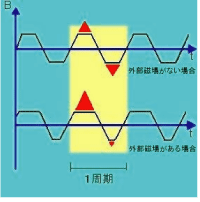
図4:外部磁場がある場合と無い場合の比較
黄色に色をつけた部分は周期的に変化させた磁場変化の1周期分に対応します。外部磁場がある場合、欠けている部分が上下で非対称になっていることがわかります。
磁力計のセンサー後段についている回路部ではこの欠けている部分を時間的に積分(足し合わせること)しています。よって、外部磁場がない場合には積分値は ゼロとなり(上下で欠けている部分が同じ)、外部磁場がある場合に積分値はある値(上下で欠けている部分の差)を示します。実際に磁場を測定するときは、 FBコイルという3つめのコイルをセンサーの一番外側に置いて、あらかじめわかっている大きさの磁場を「外部磁場とは反対の方向に」つくってやります。つ まり、FBコイルで作った既知の磁場と、外部にもともと存在していた磁場が等しい大きさになるとき回路部での積分値は0となります。そして、その時にFB コイルで作っている磁場の大きさを実際の観測値とします。
補足ですが、外部磁場がない場合とある場合で、ある場合の時は黄色で示した1周期と、磁束密度がゼロになる瞬間がずれている(黄色に塗った部分の端と磁束 密度のグラフの交点がt軸上にない)ことがわかります。実はこのずれが、最初に言っていた交流成分の2倍の周波数成分となって見えてくるのです。
<岡田和之>